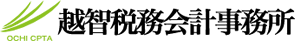相続に関する基礎知識や事例
相続という言葉を聞いて自分とは無縁、相続する人なんてひと握りなんじゃないのと感じる方は少なくないのではないでしょうか。確かに相続から連想されるのは、映画やドラマの主題になるようなばく大な遺産をイメージされる方もいるかもしれません。
しかし現在、日本では高齢化社会にともない相続に関するトラブルや相談が増えつつあるのです。さらに言うと平成27年に相続税法が改正され、今まで相続税を支払う必要のなかった人も納税の対象になりました。
改正前は全体の約4パーセント程度だった対象者が2倍の8パーセントに増加しました。割合としては少ないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、都道府県別の割合では1位が東京で15パーセントにものぼっており、10位以内には東京近郊の県がすべて入っています。
相続人の資格って?
まず、相続はどのように相続人を決めているのかをおはなししましょう。相続人になるには遺産を残した人(被相続人)に遺言書で指名され受遺者になるか、民法で定められた法定相続人になるかのふたつになります。
法定相続人は複数のひとが選ばれる可能性があるので、その中でも1から3まで優先順位をつけています。おおまかな法定相続人の範囲、順位は以下のようになります。
配偶者 被相続人の夫・妻は必ず相続人の権利がある
第1順位 被相続人の子ども、子どもが死亡している場合は孫に引き継がれる
第2順位 被相続人の両親
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
なぜ法定相続人の説明を少し詳しくさせて頂いたかというと実は相続税と密接な関わりがあるからです。
相続税っていくらから発生するの?
冒頭でおはなしさせて頂いたとおり、相続税は誰にでも発生するわけではありません。被相続人が基礎控除額を超える遺産がなければ、税金を支払う必要も申告する必要もないのです。
では基礎控除額はどのように決められているのか。ここで先ほど説明した法定相続人が重要になってきます。基礎控除額の計算方法は以下になります。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり法定相続人が多ければ多いほど基礎控額が増えることになります。
相続税が発生した場合、どうすればいいの?
被相続人の遺産が想定よりも多くなり基礎控除額を超えてしまったというケースは少なくありません。特に不動産や土地を所有している方は控除額を超えることがままあります。
相続税は相続人が死亡した翌日から10ヵ月以内に納税・もしくは申告をしなければなりません。相続の配分が決まらない場合、申告を提出すれば3年以内に期限を延ばすことが出来ますが、延ばすことによって特例というものが使えなくなるかもしれないのです。
特例には配偶者控除・小規模宅地等があります。配偶者控除は1億6000万円まで相続税がかからなくすることが出来たり、一方の小規模宅地は現在の住んでいる家の金額を最大80パーセント減額ができるものになっています。これらの特例は相続の分配に時間がかかった場合、適用されなくなる可能性があるのです。
大幅に減額される特例が利用できなくなるのはもったいない ですね。相続税が発生した場合は早め早めの対応が必要です。
税理士法人HOPEオフィスは30年以上にわたり池袋で税務・相続についてお困りの方のサポートをさせて頂いております。
これからも、お客様の一番身近な相談役として寄り添っていきたいと思っております。現在、豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。相続や贈与などでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
-

相続税の申告期限はいつ?...
相続が発生した時に相続税の申告を行いますが、相続税の申告納税期限は相続が発生してから10か月以内となっています。相続税の申告納税までには財産目録を作成して遺産分割協議を行って遺産の分割を行うことになりますが、相続人間でト […]
-

不動産が相続税対策になる...
「父親の相続財産の中に不動産が含まれていたが、相続税はどのくらいかかるのだろうか」「不動産は相続税対策になると聞いたことがあるが、なぜ対策になるのだろう」「相続税対策はどこに相談すれば対応してもらえるのだろう」。相続税に […]
-

相続税の申告漏れがあった...
「相続税の申告書に漏れがあることが判明したが、どのようなペナルティが課せられるのか」「事前に相続税に申告漏れがないかどうか確認してもらうことはできないのか」「そもそも相続税納税の義務があるかどうかが分からない」。相続税に […]
-

税務署から「相続税のお尋...
相続の発生後、しばらくすると税務署から「相続税のお尋ね」という書類が届く場合があります。この書類は相続税を申告する必要があるか否かをチェックできる書類であり、無視してしまうと、知らず知らずのうちに相続税の滞納などトラブル […]
-

相続税の連帯納付義務とは...
複数いる相続人のうち、誰かが相続税を支払わなかった場合、相続税の納付義務はどうなるのでしょうか。そんな事態を想定して、相続税には、「相続税の連帯納付義務」という制度と義務が存在します。本記事では、この「相続税の連帯納付義 […]
-

自動車の相続税はいくら?...
自動車も相続税課税対象の財産です。被相続人が有していた財産の中に自動車が含まれているときは、自宅や宅地、現金、預貯金などの財産と同じように相続税の計算に含めなければなりません。 当記事では、自動車と相続税の関係について言 […]
-

【税理士が解説】相次相続...
相続の際には、相続財産に応じて相続税を支払う必要があります。しかし、相続が短い期間内で複数回発生してしまうとその分だけ相続税を支払う回数も増えてしまいます。短期間に複数回の相続が起こった際に相続税の負担とならないために相 […]
-

持株会社を利用した事業承...
事業承継は会社経営者にいつかやってくる大きな課題です。株式会社であれば、経営に支障をきたすことなく、そして過大な税負担がかからないようにするため、どうやって株式を移転させるかがポイントとなります。よくあるのは相続や贈与に […]
-

特別寄与料とは?計算方法...
相続においては、被相続人の財産を法定相続分や公平に分割することでトラブルを防ぐことを行っていきますが、中には被相続人の介護を無償で行っていたということなどで相続人ではない人が対価を求める場合があります。この際に請求される […]
-

【税理士が解説】相続税申...
相続手続きの中には相続税の申告も含まれますが、申告時には多くの添付書類が必要となります。では、相続税申告の際に必要な添付書類にはどのようなものがあるのでしょうか。本稿で詳しく見ていきましょう。必ず必要になる添付書類まず一 […]
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
保険の非課税枠を活用...
生命保険には非課税枠が存在し、それを利用することで生前対策を行うことが可能です。保険金には相続税が課税されることになりますが、本来遺された方々の生活のための財産ということもあって非課税枠が設定されています。非課税限度額は […]

-
事業承継にかかる税金...
事業承継を行う際、主に贈与税や相続税が発生します。場合によっては所得税や登録免許税、不動産取得税が発生することもありますので、課税される税金の種類とその負担額についてはあらかた把握した上で手続を進めていくことが大事になっ […]

-
相続税の基礎控除額は...
相続税における「基礎控除」とは、相続財産のうち一定額までを課税対象から除外する制度です。多くの場合、遺産の総額が基礎控除額を上回らないため相続税が課されないのですが、その判定をするにはまず基礎控除額を把握できないといけま […]

-
生命保険を活用した相...
相続対策として生命保険を活用するのは、有効な手段のひとつです。本記事では、生命保険を活用した相続対策の仕組みや注意点について解説します。生命保険を活用した相続対策の仕組み生命保険を利用して相続対策をする場合、受取人が相続 […]

-
二次相続を考慮した有...
相続の際には、今目の前で起こっている相続に対してどのように問題を解決していくかということに注力していくことになります。しかし、相続を行う際には「二次相続」のことも考えながら相続を行う必要があります。二次相続とは今起こって […]

-
相続税対策として養子...
相続対策として養子縁組をするということがあげられます。しかし、養子縁組はすればするほど相続税対策になるわけではなく、仕組みを理解しておかないと思わぬ結果を招く可能性があります。本稿では、相続税対策として養子縁組を行うメリ […]

Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |