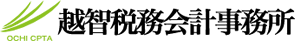相続税の申告はどんな場合に不要?着目するポイントを紹介
相続税の申告は必須ではありません。実際、相続人になった方のうち大半は申告を行っていません。なぜなら一定以上の遺産総額がなければ相続税は発生せず、申告も不要になるからです。
では遺産の額がいくら以下なら申告は不要になるのでしょうか。遺産の大きさ以外も申告の必要性にかかわってきますので、ここで紹介していきます。
相続税の「基礎控除」がポイント
相続税の計算を進めるとき、基礎控除を適用します。様々な控除制度がありそれぞれ適用要件などが細かく設定されていますが、基礎控除については誰でも適用を受けることができます。
相続税の特徴として、“基礎控除額が比較的高額である”ということが挙げられます。
最低でも3,000万円、それ以上の控除額を適用させられることも珍しくないため、数千万円以上の財産が相続されることになっても非課税で取得できるケースが多いのです。
遺産の総額が基礎控除額以下なら申告不要
基本的に相続税の申告が必要になるのは納付すべき税額が発生する場合です。遺産が一切ない場合は当然相続税も発生しませんが、それなりに大きな遺産があるときでも基礎控除の適用を受けて課税価格が0円になればやはり相続税は発生しません。
よって、次の関係性にあるといえます。
遺産の大きさと控除額のバランス | 申告の必要性 |
|---|---|
遺産の総額 > 基礎控除額 | 必要になる可能性がある |
遺産の総額 < 基礎控除額 | 不要 |
なお、遺産の総額の方が大きい場合でも申告が必要になるとは限りません。他の税額控除の適用を受けた結果納付額が0円になり、かつ当該控除についての申告が必要ないときは、申告が不要となります。
基礎控除額の計算方法
相続税に関する基礎控除の大きさは、次の計算式で求まります。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 法定相続人がいないとき:3,000万円
- 法定相続人が1人のとき:3,600万円
- 法定相続人が3人のとき:4,800万円
- 法定相続人が5人のとき:6,000万円
このように、法定相続人が多いほど多額の控除が可能となり、申告が必要になる可能性も低くなります。
遺産の総額の計算方法
ここでの「遺産の総額」は「正味の遺産額」のことを指しており、その価額を調べるにはすべての遺産から非課税財産や債務などを差し引く必要があります。
一方で純粋な相続財産ではないものの、生前贈与加算※1の適用を受ける贈与財産の価額、相続時精算課税※2に基づく贈与財産の価額を加える必要があります。
※1 生前贈与加算:相続前3年以内(2024年以降の贈与については前7年以内)の生前贈与を相続税の計算に含めること。
※2 相続時精算課税:贈与時ではなく相続時に税金の精算を行うことを選択したときの課税方式。
正味の遺産額を調べるにはこうした相続税に関するルールをよく理解した上で計算をしなければならず、難易度が高いです。各財産について相続税評価額を明らかにしていくことも必要であり、例えば宅地や家屋について「〇〇万円」などと金額を調べないといけません。
税額控除や特例にも注意
「未成年者控除」や「障害者控除」などの税額控除が適用できるケースもあります。そしてこれらについては適用を受けるのに申告手続が不要で、最終的に納付額が0円になるときは一切の申告が必要なくなります。
他方で「配偶者控除」「贈与税額控除」「外国税額控除」については利用するのに申告手続が必要であることから、納付額が0円になっても申告作業を省略できません。
高額な評価額が付きやすい宅地について大幅に評価減ができる「小規模宅地等の特例」についても同様です。特例によって遺産の総額が大きく変動することになりますが、利用にあたってはやはり申告が必要です。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
相続時精算課税制度を...
生前贈与を検討中の方は、相続時精算課税制度について聞いたことがあるかもしれません。令和5年度税制改正大綱によって制度の見直しがされているので、検討中の方は内容やポイントの理解を深めておくと安心です。本記事では、相続時精算 […]

-
持株会社を利用した事...
事業承継は会社経営者にいつかやってくる大きな課題です。株式会社であれば、経営に支障をきたすことなく、そして過大な税負担がかからないようにするため、どうやって株式を移転させるかがポイントとなります。よくあるのは相続や贈与に […]

-
合資会社と株式会社で...
合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在する持分会社で、有限責任社員しかいない株式会社とは性質が大きく異なります。その違いは両社の事業承継の方法にも反映され、進め方や採れる選択肢には差があります。合資会社での事業承継の […]

-
生前贈与は遺留分侵害...
相続対策として生前贈与を行うことによって相続税の節税対策を行うことが出来ます。しかし、相続の際には特定の相続人にほとんどの遺産が渡ると遺留分減殺請求によって保証された相続分である遺留分の請求が出来ます。生前贈与の場合には […]

-
【税理士が解説】相続...
相続手続きの中には相続税の申告も含まれますが、申告時には多くの添付書類が必要となります。では、相続税申告の際に必要な添付書類にはどのようなものがあるのでしょうか。本稿で詳しく見ていきましょう。必ず必要になる添付書類まず一 […]

-
孫への生前贈与方法
財産が多く、相続税が心配で相続税の対策をしたいとお考えの方がいらっしゃるかと思います。相続税の対策として様々な方法がありますが、特に孫への生前贈与を活用するのは対策方法の中でも最も有効な方法の一つです。 孫への […]

Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 生前対策 相談 税理士 目黒区
- 相続税申告 相談 税理士 板橋区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 生前対策 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 目黒区
- 池袋 相続税対策
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 生前贈与 相談 税理士 練馬区
- 生前対策 相談 税理士 板橋区
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
- 池袋 贈与税
- 贈与税申告 相談 税理士 板橋区
- 贈与税申告 相談 税理士 豊島区
- 相続対策 相談 税理士 豊島区
- 相続税申告 相談 税理士 目黒区
- 相続税申告 相談 税理士 豊島区
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 板橋区
- 生前対策 相談 税理士 練馬区
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |