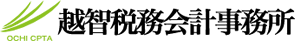生命保険を活用した相続対策の仕組みや注意点
相続対策として生命保険を活用するのは、有効な手段のひとつです。
本記事では、生命保険を活用した相続対策の仕組みや注意点について解説します。
生命保険を活用した相続対策の仕組み
生命保険を利用して相続対策をする場合、受取人が相続人である必要があります。
受取人が相続人でないときは、相続対策となる非課税枠が適用されないので注意が必要です。
また、非課税限度額は「500万円×法定相続人の人数」の計算式で算出されます。
この非課税限度額の範囲内であれば、受け取った保険金に相続税は課されません。
これらの仕組みが、生命保険を活用した相続対策の内容です。
相続税対策で生命保険を活用するメリット
相続税対策はさまざまありますが、生命保険を活用するメリットは以下の通りです。
- 生命保険の非課税枠を利用できる
- 生命保険金の受取人を指名できる
- 受け取った保険金を納税資金に充てられる
- 生命保険金は相続放棄しても受け取ることができる
- 親から子への生前贈与としても活用できる
生命保険金の受取人を指名できると、保険金は受取人の固有財産となるので遺産分割協議が必要ありません。
よって相続人同士のトラブルを減らす効果が期待できます。
また、相続税の納税は現金で納める必要があるので、納税資金が相続人の負担となる可能性があります。
生命保険の保険金は現金で手元に入るため、納税資金として活用できるメリットがあります。
さらに、相続放棄すると相続財産を受け取れなくなりますが、保険金は受取人の財産とみなされるので受け取ることができます。
ただし、非課税枠については相続人の権利であるため利用できなくなる点に注意してください。
最後に、親を被保険者、子を契約者かつ受取人とする生命保険では、生前贈与としての活用が可能です。
贈与税の非課税枠年間110万円以下を子に贈与し、それを保険料の支払いに使います。
保険金は子が受け取り、かつ契約者も子なので、保険金は相続税ではなく所得税が課税されます。
相続税と所得税でどちらが得なのか試算してから、検討してください。
生命保険を活用した相続対策の注意点
生命保険の種類はたくさんありますが、相続税対策に使える生命保険を選ぶ必要があります。
生命保険はおおまかに定期保険、養老保険、終身保険の3種類がありますが、もっとも相続対策に適しているのは終身保険といわれています。
また、生命保険の特約には生前給付型のものがあり、生前の治療費に充填できる利点はありますが、相続対策には向いていません。
生命保険を活用した相続税対策には、死亡保険金が受け取れる保険を選ぶようにする必要があります。
まとめ
今回は、生命保険を活用した相続対策の仕組みや注意点について解説しました。
生命保険を活用すると、非課税限度額を利用した相続対策が可能です。
しかし、相続対策に適した生命保険の種類を選択しなければいけません。
生命保険を活用した相続対策に関心のある方は、税理士へ相談することを検討してみてください。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
小規模宅地の特例とは
相続税は小規模宅地等の特例を使うことによって、税額を低くすることができます。小規模宅地の特例を利用できるものは次のようなものになります。 ①特定居住用宅地等この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのた […]

-
事業承継にかかる税金...
事業承継を行う際、主に贈与税や相続税が発生します。場合によっては所得税や登録免許税、不動産取得税が発生することもありますので、課税される税金の種類とその負担額についてはあらかた把握した上で手続を進めていくことが大事になっ […]

-
相続税の時効とは
相続税を申告することをすっかり忘れていたといった場合にも。数十年前の相続税を支払わなければならないということはありません。相続税には時効が存在しており、時効が成立したものに関しては、相続税は支払わなくてもよいことになって […]

-
贈与税申告の必要書類...
贈与により、1年間で 110万円を超える額の財産を取得した方は、原則として贈与税の申告をしなければなりません。 このとき必要となる添付書類等をここで紹介し、納税の方法についてもあわせて解説していきます。 必要書類1:贈与 […]

-
相続税申告を税理士に...
相続税申告を税理士に依頼することによって、税理士は次のようなことが対応可能となります。・相続税の申告代行相続税の申告を税理士に依頼をすることが出来ます。相続税の申告書の記入は非常に面倒なものとなることもあります。そのため […]

-
特別寄与料とは?計算...
相続においては、被相続人の財産を法定相続分や公平に分割することでトラブルを防ぐことを行っていきますが、中には被相続人の介護を無償で行っていたということなどで相続人ではない人が対価を求める場合があります。この際に請求される […]

Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 生前対策 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 練馬区
- 贈与税申告 相談 税理士 文京区
- 相続対策 相談 税理士 目黒区
- 相続対策 相談 税理士 豊島区
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 板橋区
- 生前贈与 相談 税理士 豊島区
- 贈与税申告 相談 税理士 目黒区
- 相続対策 相談 税理士 文京区
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 板橋区
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
- 生前対策 相談 税理士 目黒区
- 生前対策 相談 税理士 板橋区
- 相続税申告 相談 税理士 目黒区
- 贈与税申告 相談 税理士 豊島区
- 池袋 相続税
- 池袋 贈与税
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |