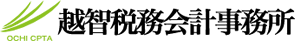相続税の2割加算とは? 割増しで負担がかかる人の判定と計算時の注意点について
亡くなった方との関係性が遠い場合、配偶者や子どもなどに課税される相続税とは計算方法が少し異なります。「2割加算」と呼ばれる処理が必要で、税負担が割り増しでかかってくることに留意しなくてはなりません。
当記事ではこの2割加算についての「計算方法や計算時の注意点」、そして「加算対象になる人」について説明をしています。
相続税の2割加算のルール
2割加算が適用される場合の計算方法や注意点など、基本的なルールを以下にまとめます。
各自の相続税額に「1.2」を掛けて納付額を計算する
相続税は各自が取得した遺産の大きさを基準に計算するのですが、いったん課税価格を合計して相続税の総額を計算しなくてはなりません。そこで次のような流れで相続税の総額を算出します。
- 各自が取得した遺産の課税価格を調べる
- 課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引く
- 基礎控除適用後の「課税遺産額」を法定相続分で分割する
- 法定相続分に対応した各取得金額に税率を乗じて各税額を調べる
- 各税額を合計した結果が「相続税の総額」
相続税の総額が明らかになれば、ここで各自の実際の取得割合であん分し、各自の相続税額を導き出します。法定相続分が1/2でも実際の取得割合が1/3なら、相続税の総額に1/3を乗じて各々の相続税額が計算されます。
ただ、配偶者控除や未成年者控除などの税額控除が使える方はその分を差し引く必要がありますし、亡くなった方との関係性(血族関係)によっては税額控除を適用する前に「2割加算」しないといけません。
2割加算の処理自体は簡単です。もし算出された相続税額が100万円であれば「100万円×1.2=120万円」、500万円であれば「500万円×1.2=600万円」と、「1.2」を掛ければ良いのです。
税額控除適用との順序に注意
このときは税額控除の適用との順番に注意が必要です。先に2割加算をする必要があり、この順番を逆にしてしまうと本来より小さな税額で申告・納付をすることになってしまいます。
なぜ加算するのか
亡くなった方との血族関係が遠い場合、あるいはまったく血のつながりがない場合にこの2割加算は行われるのですが、その理由として大きく次の3つが挙げられます。
- 財産を取得したことに関して偶然性が高く担税力が強いとみられるため
- 遺産形成への貢献度が低いとみられるため
- (孫が遺産を取得する場合)子どもを越して孫が財産を手にすると相続税の課税を1回分免れるため
実際のところ、血のつながりが遠いからといって常にこれらの理由が適しているとも言い切れません。しかし相続による利益の調整を図るため、一定の範囲内に入るかどうかで区別して、2割加算の適用有無を判断する運用がなされています。
2割加算の対象者
2割加算の対象になるのは「一親等の血族・配偶者以外の者」です。
一親等の血族とは、亡くなった方を基準に考えてその子どもや親のことであり、祖父母や兄弟姉妹、孫についてはその範囲外となります。
相続人になれる人の優先順位としては第1に子どもが挙げられ、同時に配偶者も相続人になることができます。このケースにおいては誰も2割加算の対象にならないのですが、遺言書を作成しておりその他友人などの相続人以外の者へ遺産を渡すときは2割加算の処理が必要となりますので注意が必要です。
| 2割加算 |
|---|---|
配偶者 | ― |
子ども | ― |
父母 | ― |
祖父母 | 対象 |
兄弟姉妹 | 対象 |
孫・ひ孫 | 対象 ※子どもを代襲相続するときは対象外 |
甥・姪 | 対象 |
義理の父母 | 対象 |
友人・知人 | 対象 |
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
相続税申告を税理士に...
相続税申告を税理士に依頼することによって、税理士は次のようなことが対応可能となります。・相続税の申告代行相続税の申告を税理士に依頼をすることが出来ます。相続税の申告書の記入は非常に面倒なものとなることもあります。そのため […]

-
生前贈与の手続は自分...
生前贈与は相続対策として有効な手段です。専門家に相談をしたり手続の代行を依頼したりすることが多いですが、自分ですることも可能です。ただし自分自身でやるべきことが多くなりますので、何の手続・作業が必要になるのかは把握してお […]

-
準確定申告とは?期限...
準確定申告とは、被相続人が得た所得を、相続人が計算・申告することを指します。通常の確定申告は、前年度の所得等を翌年の2月16日から3月15日までに申告しますが、申告が必要な人が年度の途中で亡くなった場合、相続人がその手続 […]

-
【税理士が解説】相続...
相続が発生したとき、どのように処理した方がよいのか迷うのが「不動産」です。不動産を相続すると、維持管理が大変なため売却を検討する方も多いでしょう。本記事では、相続した不動産を売却するメリットについて解説します。相続した不 […]

-
【2023年度税制改...
相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正により改正されました。これにより、死亡日から遡って相続税の課税対象となる期間が3年から7年へと延長されました。また、このことはこれまでの相続税対策や相続税の計算にさまざまな影 […]

-
結婚・子育て資金一括...
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、子や孫の結婚・出産を支援するための贈与については1000万円までを非課税とする制度です。この制度は平成27年から始まり当初は平成31年までの利用が限度でしたが、平成31年度の税制改 […]

Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 生前対策 相談 税理士 目黒区
- 相続対策 相談 税理士 板橋区
- 生前贈与 相談 税理士 目黒区
- 贈与税申告 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 目黒区
- 生前贈与 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 豊島区
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 豊島区
- 池袋 生前贈与
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 生前対策 相談 税理士 豊島区
- 池袋 贈与税
- 生前贈与 相談 税理士 板橋区
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 贈与税申告 相談 税理士 目黒区
- 相続対策 相談 税理士 文京区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 相続対策 相談 税理士 目黒区
- 生前対策 相談 税理士 文京区
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |